便秘解消にはどんな方法が効果的?おすすめの食べ物や飲み物、マッサージ方法も

便秘とは、本来排出される便が大腸に留まってしまう状態のことを指します。便秘に悩む方は多いですが、実は便秘を放置していると健康へ悪影響を与えたり肌荒れを引き起こしたりすることもあるため注意が必要です。
そこで本記事では、便秘の種類や主な原因に加えて、食事や運動、マッサージなど、今日から取り入れられる便秘解消法をわかりやすく解説します。
【基礎知識】そもそも便秘とは?

便秘とは、本来排泄されるべき便が大腸内に留まってしまうことで、排便回数が減少したり、排便時に過度な怒責(いきみ)や残便感などが生じたりする状態のことです。
簡単にいうと、「便が硬くて出にくい」「排便回数が少ない」「出そうと過度にいきむ」「出てもすっきりしない」といった症状がある場合を便秘と呼びます。
一般的には4~5日以上排便がないと便秘とされますが、便通は個人差が大きいものです。そのため、人によっては1~2日排便がなくても不快感がなければ便秘とはいえません。
一方で、毎日排便があっても排便量が少なかったりすっきり感が得られなかったりすれば便秘に該当することもあります。
また、このような便秘状態が長期間(目安として3か月以上)続き、学業や就労、睡眠など日常生活に支障をきたすほどの症状を伴う場合を「慢性便秘症」といいます。
(参照元)日本予防医学協会|冬は便秘になりやすい!? 、一般社団法人 愛知県薬剤師会|5.便秘
便秘の主な種類・分類

便秘はさまざまな要因で引き起こされ、それぞれに解消法・対処法が異なります。まずは便秘の主な種類や分類から見ていきましょう。
ひとことに便秘といっても、まずは大きく「機能性便秘」「器質性便秘」「症候性便秘」「薬剤性便秘」の4つに分類されます。それぞれの概要は、以下の通りです。
| 便秘の種類・分類 | 概要 |
|---|---|
| 機能性便秘 | 生活習慣やストレス、加齢などの影響によって、大腸や直腸・肛門の働きが乱れることで生じる便秘 |
| 器質性便秘 | 大腸がんや手術後の癒着、炎症性疾患(潰かいよう瘍性大腸炎やクローン病)などが原因で生じる便秘 |
| 症候性便秘 | 甲状腺機能低下症や副甲状腺機能亢こうしん進症による大腸のぜん動運動の低下が原因で生じる便秘。生理や妊娠中のホルモンの影響による便秘も、症候性便秘に分類される |
| 薬剤性便秘 | 特定の薬剤の副作用による便秘 |
中でも、一般的によく見られるのは、生活習慣やストレス、加齢が影響している「機能性便秘」です。機能性便秘も、大腸や直腸、肛門の働きが乱れる原因によって、さらに「弛緩性便秘」「けいれん性便秘」「直腸性便秘」3つのタイプに分けられます。
ここからは、それぞれの特徴について詳しくご説明します。
(参照元)一般社団法人 日本臨床内科医会|わかりやすい病気のはなしシリーズ49 便秘
弛緩性便秘

「弛緩性便秘」とは、大腸のぜん動運動の低下が原因で生じる便秘のことです。
大腸は便をぜん動運動で少しずつ直腸へ送り、水分を吸収しながら排泄へ導きます。しかし、大腸を動かす筋肉の緊張が低下してぜん動運動が弱まると、便の通過に時間がかかりすぎてしまいます。
そのため、大腸で水分が過剰に吸収されてしまい、便中の水分量が減って硬くコロコロとした状態になってしまい、結果として便秘が引き起こされるのです。
弛緩性便秘は、高齢者や出産後の女性に多い傾向があります。
(参照元)市立御前崎総合病院|便秘の種類、一般社団法人 日本臨床内科医会|わかりやすい病気のはなしシリーズ49 便秘
けいれん性便秘
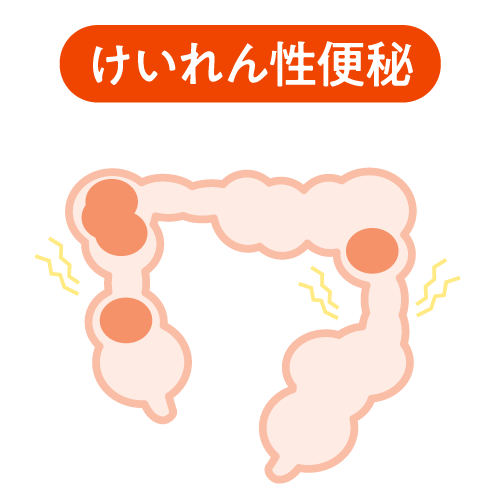
「けいれん性便秘」とは、自律神経の乱れによる大腸のけいれん的収縮が原因で生じる便秘のことです。
過敏性腸症候群に伴うことが多く、過度なストレスなどがかかることで、大腸のぜん動運動が断続的に収縮・拡張を繰り返してしまいます。その結果、腸管が部分的に狭くなって便の通過に時間がかかり、大腸で水分が過剰に抜かれてコロコロとした小粒の便が出やすくなるのです。
また、けいれん性便秘では、下痢と便秘を繰り返し、排便前に腹痛を伴うこともあります。過度なストレスや緊張を感じやすい方に見られやすいタイプです。
(参照元)市立御前崎総合病院|便秘の種類、一般社団法人 日本臨床内科医会|わかりやすい病気のはなしシリーズ49 便秘
直腸性便秘

「直腸性便秘」とは、直腸の排便を促す反射(排便反射)の鈍化が原因で生じる便秘のことです。
便が直腸に届くと便意が起こりますが、習慣的に便意を我慢したり、下剤・浣腸を乱用したりすると、直腸の感覚が鈍くなり排便反射が弱まってしまいます。その結果、便意を感じにくくなり、排便がさらに先延ばしになって便が硬くなるのです。
トイレを我慢しがちな方や、生活習慣が乱れて朝のトイレタイムに時間的余裕がない方に見られるタイプです。また、温水便座の過度な使用によって神経の感度が鈍ることでも、直腸性便秘が引き起こされる場合もあります。
(参照元)市立御前崎総合病院|便秘の種類、一般社団法人 日本臨床内科医会|わかりやすい病気のはなしシリーズ49 便秘
便秘を放置したときのリスク

「たかが便秘」と安易に考えて便秘を放置してると、大腸内で便がますます硬くなります。そして、硬い状態の便が長く留まることによって、直腸潰瘍や脱肛、直腸粘膜脱といった健康リスクが生じることもあるため注意が必要です。
また、便が固まってしまう「便塞栓症」を招き、器具を使ってかき出さなければいけない場合もあります。さらにごくまれに大腸に穴(穿孔)が開き、腹膜炎を起こす危険もあるのです。
慢性的な便秘は、冠動脈性心疾患や脳卒中など全身疾患のリスクを高める可能性があるほか、肌荒れや身体的・精神的なQOL(生活の質)、労働生産性の低下にもつながるため、早めの対策が必要です。
なお、以下のような症状が見られた場合は、速やかに医療機関を受診してください。
- ・強い腹痛や吐き気、発熱を伴う便秘
- ・体重減少を伴う慢性的な便秘
- ・血便 など
(参照元)日本予防医学協会|冬は便秘になりやすい!?、一般社団法人 日本臨床内科医会|わかりやすい病気のはなしシリーズ49 便秘
便秘につながる主な原因5つ

便秘の原因はさまざまですが、ここでは一般的によく見られる「機能性便秘」の原因を詳しく見ていきましょう。
- ●食物繊維不足
- ●水分不足
- ●運動不足
- ●過度な緊張やストレス
- ●生活習慣の乱れ
食物繊維不足
食物繊維は、体内で消化されない栄養素です。便の体積を増やすとともに、腸内環境の改善に役立つ腸内細菌のエサとなるため快便には欠かせない栄養素でもあります。
食物繊維の摂取が不足してしまうと、便のかさが減少して排便しにくくなります。さらに、食物繊維の不足は腸内環境の悪化を招き、生活習慣病のリスクを高める可能性もあるので注意が必要です。
(参照元)厚生労働省|食物繊維の必要性と健康
水分不足
通常、飲料や食事から摂取した水分は小腸で吸収されたあと、一部が大腸へ送り込まれ便をやわらかく保つ働きを担います。
しかし、体内の水分が不足すると大腸が余分に水分を吸収してしまい、便は乾燥して硬く、コロコロとした状態になってしまい便秘を引き起こしてしまいます。
のどの渇きを感じにくかったりトイレを気にして水分摂取を控えたりしがちの方は、水分不足による便秘リスクが高まるため、注意しましょう。
(参照元)一般社団法人 日本臨床内科医会|わかりやすい病気のはなしシリーズ49 便秘
運動不足
適度な運動は腹部周りの筋肉を刺激して腸管を押し動かし、排便を促進します。
しかし、長時間のデスクワークや運動習慣のない生活では腸の動きが鈍くなり、便が大腸内に長く滞留して便秘を引き起こすことがあります。
(参照元)一般社団法人 愛知県薬剤師会|5.便秘
過度な緊張やストレス
過度な緊張やストレス、自律神経の乱れは、大腸の運動に影響を与え、下痢や便秘を交互に引き起こすこともあります。
また、大腸でけいれん収縮が生じて腸管が狭くなり、便の通過が遅くなることで便が硬くなってしまう「けいれん性便秘」も緊張やストレスが主な原因とされています。
(参照元)一般社団法人 愛知県薬剤師会|5.便秘
生活習慣の乱れ
腸のぜんどう運動は、交感神経が優位なときは抑制され、副交感神経が優位なときに活発になります。
しかし、生活習慣が乱れてしまうと、交感神経と副交感神経の切り替えがうまくいかなくなってしまう可能性が高まります。それに伴い、腸の蠕動運動にも影響を与えて、便秘を引き起こすことも。
また、生活習慣が乱れてしまうと、朝の決まった時間にトイレに行く習慣などもつきにくく、便意を我慢してしまうケースも見られるため注意しましょう。
(参照元)神奈川県衛生研究所|運動とおなかの調子
便秘解消に効果的なおすすめの方法【腸活がカギ】

気になる便秘を解消するためには、腸内環境を整える「腸活」の視点も重要です。
発酵食品や食物繊維の摂取、水分補給、適度な運動、マッサージに加えて、腸内の善玉菌を増やし、腸内フローラを整える取り組みが注目されています。
ここからは、日常生活に取り入れやすい5つの腸活方法を紹介します。
腸内環境を整えるには「食べ物」の見直しがカギ!5つの効果やおすすめの改善方法も紹介
腸活とは?男性・女性必見のメリットや効果的なやり方・食べ物・NG行動も解説
食物繊維や発酵食品を積極的に摂取する
便秘解消のためには、まずは食生活の見直しから始めてみましょう。
とくに、以下のような栄養素を意識して摂取することで、腸内の善玉菌を増やし、排便リズムを整える効果が期待できます。
それぞれ、詳しく解説します。
食物繊維
日本人の食事摂取基準(2025年版)によると、1日の食物繊維の摂取量の目標量は以下の通りです。
| 年齢 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 18歳~29歳 | 20g/日以上 | 18g/日以上 |
| 30歳~64歳 | 22g/日以上 | 18g/日以上 |
| 65歳~74歳 | 21g/日以上 | 18g/日以上 |
食物繊維を積極的に摂るためには、主食を玄米ごはん、麦ごはん、胚芽米ごはん、全粒小麦パンなどに置き換えたり、豆類、野菜類、果実類、きのこ類、海藻類を取り入れた献立を考えたりする方法がおすすめです。
また、効率的に食物繊維を摂取するためには、サプリメントを活用する方法もあります。
(参照元)厚生労働省|食物繊維の必要性と健康、厚生労働省|「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
オリゴ糖
オリゴ糖は腸内に生息する善玉菌のエサとなり、とくにビフィズス菌を増やす働きがあることが知られています。ビフィズス菌が優位な状態になることで腸内環境が整い、便通の改善にもつながります。
オリゴ糖は、はちみつや野菜(ブロッコリーやたけのこ)、果物類にも含まれているため、日常の食事に取り入れやすい成分です。毎日の食卓で自然に摂取できる食品を意識して選ぶことで、腸内フローラのバランスを整えるサポートが期待できます
(参照元)厚生労働省|食物繊維の必要性と健康
発酵食品(ビフィズス菌・乳酸菌)
ヨーグルトや味噌、ぬか漬け、納豆などの発酵食品には、乳酸菌やビフィズス菌といった善玉菌が含まれています。これらの微生物は、発酵の過程で糖類から乳酸をつくり出す性質を持ち、腸内の環境を整えるうえで重要な役割を果たします。
発酵食品を継続的に摂取することで、腸内を善玉菌優位な状態に保ちやすくなり、排便リズムの改善や便秘予防に役立ちます。食事の一部として取り入れることで、無理なく腸活を続けられるのも大きなメリットです。
(参照元)厚生労働省|乳酸菌(にゅうさんきん)
適度に水分を補給する
水分が不足しないように、適度な水分補給を意識することも大切です。
1日の水分量の基準値は明確には定められていませんが、一般的に1日の水分の出入りは約2.5Lとされており、そのうち食事での水分摂取が1.0L、飲み水での水分摂取は1.2Lが目安とされています。
水分は喉の渇きを感じてから飲むのではなく、渇きを感じる前にこまめに飲むことがポイントです。水分補給の際は、糖分が含まれる清涼飲料水は避けて、水やノンカフェインのお茶類などがおすすめです。
ストレッチや軽い運動を取り入れる
便秘解消のためには、ストレッチや軽い運動を取り入れましょう。激しい運動ではなく、ウォーキングやランニングといった有酸素運動、腹筋や骨盤の筋肉にアプローチする筋トレなどがおすすめです。
また「ねじり」運動を取り入れたストレッチも、腸管を刺激し、自律神経のバランスを保つ効果が期待できるとされています。
(参照元)日本大腸肛門病会誌 72:621-627,2019|慢性便秘症に対する食事療法,運動療法,理学療法、日本予防医学協会|冬は便秘になりやすい!?
マッサージをする
腸のぜんどう運動をサポートするためには、マッサージも効果的です。
仰向けになり腹部を「の」の字を書くようにマッサージし、左右の脇腹を上下に揉んでみましょう。さらに、下腹部を上に押し上げるように圧迫して腸を刺激する、といった方法も一般的です。
(参照元)日本大腸肛門病会誌 72:621-627,2019|慢性便秘症に対する食事療法,運動療法,理学療法
サプリメントを取り入れる
便秘解消に向けて、日々の食事で食物繊維や発酵食品などを摂取したり運動を取り入れたりすることは大切です。しかし、毎日忙しい生活の中で、食事を長期的に見直すのは難しいこともあります。
そんなときは、生活習慣の見直しに加えて、サプリメントを活用する方法もおすすめです。サプリメントは、食事の前に水と一緒に飲むだけで、普段の食事を楽しみながら腸活をサポートできるのが魅力です。
不足しがちな栄養素を効率良く補えるため、食生活の改善や運動などと組み合わせながら無理なく取り入れることで、便秘解消に向けた対策をより続けやすくなります。
まとめ :便秘解消には食事や運動、マッサージが大切
便秘とは、本来排泄されるべき便が大腸内に留まり、排便回数の減少や硬便、残便感などが生じる状態を指します。
便秘の原因はさまざまですが、代表的なものとして食物繊維や水分の不足、運動不足、ストレス、生活習慣の乱れなどがあげられます。これらが重なることで腸の働きが鈍り、慢性的な便秘につながるケースも少なくありません。
便秘を予防・改善するためには、食物繊維や発酵食品を取り入れたバランスのよい食事、こまめな水分補給、軽い運動やストレッチ、マッサージなど、日常生活の工夫や腸活が大切です。
そのうえで、より効率的なケアを行いたい場合には、サプリメントを上手に取り入れる方法も検討してみましょう。




